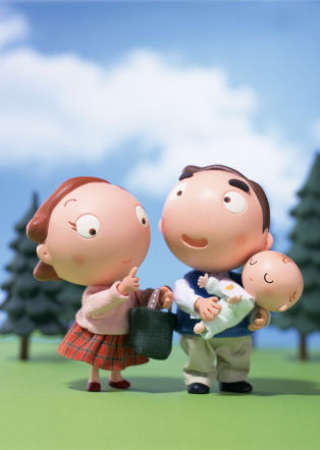日常診療からみた親子関係(2)
親としての責任
断っておくが、今回の親子の事例には、養護学級や支援学校に通学している子や自閉症の子はもちろん除いている。通常の学校に通学し、クラブ活動もして問題行動を起こしていない、所謂普通の子供である。
前回の母親が進んで説明する場合、子供の反応は2型に分かれる。一つは親に任せきりの型、もう一つはイヤな顔をしながら親の説明を聞いている型である。後者の場合は、親の子供に対する認識と子供の自我の芽生えとのバランスが悪いだけで、両者を見ていて微笑ましくなる。問題なのは前者の型で、おそらくたっぷりと飴(愛情)を注がれたのだろう。社会人になって大丈夫か心配になる。
親子とも説明しようとしない場合が一番厄介である。子供が会話出来ない、目上の人に対して丁寧語を話せないことも問題だが、困ったことがあって受診している子供を支援しない親が何よりも問題である。この場合、子供はもちろん、親も大丈夫か不安になる。おそらく、この親も両親に同じように躾けられて来たのだろう、まさに「躾のデフレスパイラル」である。道徳・倫理観の欠如が叫ばれて久しい今日の日本で、その原因の一端を日常診療から垣間みたような気がした。
今までの話は未成年の話で、ある意味しかたがなく寛容的にならなければと自分に言い聞かせ対応しているが、成人の場合はそうはいかない。ついて来た母親が終始しゃべる場合、「すいません、患者さんは子供さんなので本人にしゃべらせていただけませんか。子供さんに対する過干渉が症状の一端になっているかもしれませんよ。」と釘を刺す。
開院してから、唖然とする出来事に遭遇した。親に連れられて子供(もちろん成人)が内視鏡検査を受けに来た。問診中も無言、検査を終えて説明しても無言だったので「あなた、社会人としておかしいですよ。」と指摘したところ、涙を浮かべながら突然携帯電話を出して来た。「言葉では説明出来ないことを説明しようとしているのか」と考えしばらく様子を見ていたが、ただ単に携帯を触っているだけなのだ。付き添って来た親に、「いつも、こうなのですか。」と問うたところ、「いつも注意しているのですが・・・」とまるで他人事のようなそっけない返事だった。「いつもちゃんと注意していたら、こんなにはならないだろう。」と内心思ったし、この社会の病理の一端を目の当たりにさせられて、その日はしばらく「なぜだろう、何だろう」の疑問が心の中で繰り返された。
娘の学校の校長先生が言うように、自立させること、社会で生き抜いて行く力を身につけさせることが教育の要諦である。その方法に正しい方法はなく、各家庭十人十色のやり方があると思っている。
「かわいい子には旅をさせろ」「獅子は我が子を千尋の谷に突き落とす」という諺があるように、「巨人の星」「ジャングル大帝」というアニメ番組があるように、懐古主義的ではあるが、愛情ある子供の突き放しも教育の一つの方法論だと僕は考えている。親の責任放棄と揶揄非難される全寮制の男子校「海陽学園」だが、保護者会で出会った方と話せば決して責任放棄などしていない。偏差値至上主義の現代の教育に対して疑念を抱いており、むしろ子供を育てることに熱心な方々ばかりである。
最近も大阪のミナミで無差別殺人事件があったが、そのような犯罪を起こすような人間に育てない、一流大学を出ても引きこもる人間にさせない。このことが、親の子供に対する責任だと僕は考える。