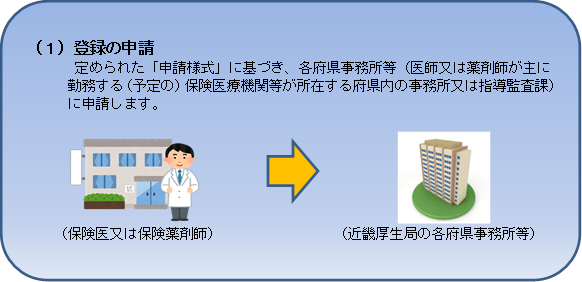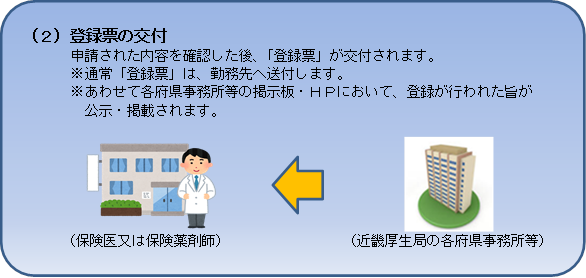ありえへん話〜本編・前編〜
これから話す内容は本当にあった話である。本来なら病院名を公表しても構わないのだが、病院運営に支障を来すことは本意ではない。医療機関を受診したこのある方及び医業経営をしている方への警鐘になれば、今回の事案を報告することにした。違った意味での引き寄せの力が僕にはある。常日頃、想定外の出来事が次々に起こっては即断即決することを求められている。いさかい事は、すなわち相手との交渉事である。結論の出ない水掛論にならないよう理論武装することを強く意識している。負ける喧嘩はしないほうがいい。自分の印象や感情は何の役にも立たない。争う時こそ冷静にならなければならない。状況証拠を積み重ねなければならない。
昨年秋、障害のある三男の定期受診があった。いつもは見ない領収書を何気なく見たところ、受けた覚えのない検査が含まれていたことに妻が気付いた。というのも、以前同様の検査を受けた際、言語能力の劣る三男をなだめるのが大変で印象に残っていたらしい。帰宅して相談を受けた僕は、「それは不正請求になる可能性があるから連絡しておいたほうがええな。忙しくて入力ミスしたかもしれんし。」とほろ酔い加減で応えた。翌日、妻が「受けていない検査を請求され支払っているんですが、」と関係部署に問い合わせた。担当医に確認して折返し連絡するとの返答は思いがけないものだった。「検査を行ったカルテ記載があります。」だった。妻は検査を受けていないと断言し、病院はしたと突っぱねる。どちらを信頼すべきか、議論の余地はあろうはずもない。定期的に行政指導を受けている受け身一辺倒の僕の心に火が点いた。「それは、カルテの不適切記載および不正請求や!保険医として許さん!」、闘うことを決めた。
当該病院の担当部署に不正請求を告発した。しかし、カルテ記載を盾に一向に聞き入れようとしない。管理管轄する病院機構にも訴えたが、暖簾に腕押し状態で聞き入れてくれているようで聞き流されている感を妻は覚えたそうだ。しびれを切らして監督官庁にも連絡をした。「ご意見は伺いましょう。」、いかにも役人対応で、「訴訟になるくらいの事案なら動きましょう。」程度の塩対応だったようだ。妻は、看護師・医師の妻・医学生三人の母というプライドからか珍しくエキサイトしている。どうすれば自分の正当性を証明できるのか、常に僕に意見を求めてくる。その後も、病院に内容証明を送付したし、電話で担当医と直接話もした。何度説明しても、結局は「やった、やらない。」の水掛論に終止し、「検査を受けた記憶が全くない。」という妻の意見に一向に耳を貸そうとしない。電話でのやり取りが主だったため、最終的には「病院に来て一度状況を説明させて欲しい。」ということになった。けれども、コロナ禍の最中である、面談は一旦破談になった。(つづく)