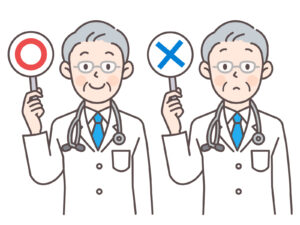医師の矜持(後編)
生活保護を受けるためには、種々の条件が求められる。(1)収入が国の定める最低生活費を下回っていること(2)持ち家や車などの資産を持っていないこと(3)怪我や病気で働けなくて生活が困窮していること(4)三親等以内の親族から支援を受けられないこと(5)公的融資制度や公的扶助の対象外にあること。我々医師は、この条件(3)に関係する。必須ではないけれども、診断書や障害者手帳を持参すると申請がスムーズに進むそうだ。「そうだ。」と他人事のように書くのは、僕自身、通院患者から生活保護申請のための診断書作成を依頼されたことがなく、また福祉事務所の担当者から相談を受けたこともないため、申請から可否の経緯についてはよく分からない。
けれども、生活保護法医療券(以下、医療券)を持った患者の診療は少なからず行っている。生活保護受給者の医療費は医療扶助により全額負担される。受給者を診療した場合、福祉事務所から送付される医療要否意見書を作成し、妥当なら支払基金から請求した医療費が支払われる。その医療要否意見書には、普通就労の可・否、もしくは軽就労可・否の項目がある。高齢で見るからに就労出来ない、または病状が重篤と判断される以外、僕は医師として普通または軽就労可に○をしている。しかし、生産人口年齢にありながら、「この人、働けるのでは?」と疑問に感じる事例が多々ある。精神疾患や専門以外の内臓系疾患は一見して病状の重さが伝わりづらく、主治医の意見を尊重し、その判断に委ねるしかない。
「不正受給かも?」を穿った見方をしてみる。主治医の立場からすれば、生活保護受給者は定期受診しなければならず、ある意味顧客。しかも、医療費全額を国が負担するので取り漏れがない。医療要否意見書で就労可とされると困るので、受給者が改善しないことを訴え続けると種々の検査がかさむ。日本の診療報酬体系は出来高制なので、それはすなわち診療所の収入増にもつながる。患者側の立場からすれば医療費がかからないので、薬局の市販薬で治るような風邪でも医療機関を受診した方がタダで済む。医師によっては、患者のいいなりに薬を処方する者もいる。こうして大量に手に入れた向精神薬を転売している事案が度々報道されたりもしている。不正受給に関しては、福祉事務所に問題があるという意見もあるようだが、医師の意見書を覆すような権限は地方公務員にはない。就労できるか困難か、すべては主治医の胸三寸にかかっている。
医師の診断書や意見書について、最近感じたことを綴ってみた。「医師(歯科含)は聖人君子ではない。」と僕は考えている。例えそうなら、警察に逮捕されたり、医業停止になるようなことなどないはずだ。単なる医学知識を持った専門家に過ぎない。しかし、その権限は絶大である。それ故、「わきまえ」が肝要だと日々自分自身に言い聞かせている。僕は、いまだ未熟で道理が分かっていないけれども、後ろ指を指されない、肩書に恥じない生き方だけはしていきたいと願っている。