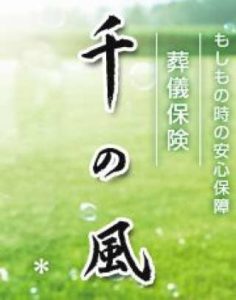葬儀に参列して
明日は我が身
時々飲み友達の経営者のホームページから拝借。
いつか、こんなところで葬儀をあげたいな、
とは、さすがに夢見られません。
| 40歳も半ばになると、葬儀に参列する機会が増えた。社会的立場による側面もあるが、我々の親の世代が亡くなる年代のようだ。 両親を若くして亡くしている自分にとって、葬儀に参列することは精神的に辛い。遺族の姿にかつての自分を投影し、その時の光景や悲痛さが蘇るからだ。しかも、僕の場合、肉体的にもこたえる。通常、通夜は19時から営まれる。平日1日1食主義の僕は、診療時間が早く終わることもあって、大体18時頃から夕食を摂る。通夜がある場合、食事開始時刻が2時間は遅れるからだ。 したがって、通夜では、故人に対する敬意と遺族とともに悲しみを分かち合いたいという気持ちと、自身のトラウマと飢餓状態がせめぎ合う。心身ともに疲弊して帰宅することもあれば、空腹感を忘れて心晴れやかに家路につくこともある。この違いは何だろう、自分なりに考えてみてたどり着いた結論は二つである。一つは、僧侶である。もっと言えば、僧侶の読経と立ち振舞が葬儀を左右する。 読経の際の音調・抑揚・拍子・旋律が、聞いていて心地いい場合とぎくしゃくさを感じる時がある。例えるなら、本チャンのラッパーが歌うラップとアイドルの歌うラップの違いである。宗派は特に関係ないが、年齢は年老いた方が有り難みがある。 振る舞いも重要である。導師入場から祭壇の前に座るまで、参列者は僧侶の一挙手一投足を注視することになる。何度も見ていれば、優雅なものから粗野なものまで分かるようになった。読経と振る舞いの素晴らしさは、正比例するようである。 ある葬儀で、読経を終えた僧侶が故人との思い出を語り出した。ぼそぼそと喋るので聞き取りづらく、話し方もたどたどしく、何よりも内容が間違っていた。帰りの車で友人と顔を見合わせて、「和尚から、あんなに有り難みのない話、聞いたこと無いな、ありえへんで。」となった。たくさんの方が参列していただけに、残念な通夜の一つになった。 葬儀では、喪主の挨拶が最も重要である。僧侶の良し悪しを凌駕し葬儀を左右する。 この文脈で考えると、末恐ろしくなってきた。同業者から疎まれ、友人も少ない僕の葬儀に参列してくれる人は、おそらくいないだろう。クリニックスタッフも、金の切れ目は縁の切れ目、はい、さようならである。そもそも、日頃から妻子に厳しくしているので、「うるさい奴が、とうとうおらんくなったな。」の一言で葬儀もしてくれないだろう。 |
| 千の風になるのも、近頃は大変ですね。 |